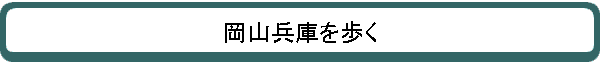
| 岡山,兵庫,大阪と滋賀を歩く |
| 2018年6月1日作成 伊藤記 |
|
2018年5月に大阪で開催される学校のクラス会に合わせ,備中松山,倉敷,岡山,姫路,神戸,大阪,安土と彦根を散策した。家を朝の7時頃に出発し岡山の備中松山城を目指し,1時前にJR備中高梁に到着した。備中松山城天守閣は小松山(約430m)の山頂にあるが,8合目のふいご峠までタクシーに乗り,そこから急な山道を20分ほど歩き天守閣に到着した。とてもではないが観光でなく山登りだ。備中松山城の天守閣は高さ11mほどの構築物で現存天守12城のなかでも最も低い。1階には囲炉裏があり,外壁の板張りが縦に貼られているのも珍しい。 |
 |
 |
 |
| 備中松天城大手門跡 | 備中松山城天守閣 | 倉敷大原美術館 |
|
この天守閣は現存する12天守閣のなかで最も高所にあり重要文化財になっている。徳川時代の1681年水谷勝宗が現天守閣を建造したが,天守閣や本丸は麓の城下町から約300mも高く,歩いて1時間程かかるので,藩主は通常城下町の御根小屋(おねごや)という館で、生活や政治をした。明治時代に多くのお城が解体され民間に払い下げられたが,このお城は山の上にあるため買い手がなく解体を免れた。約2時間のお城見学後,倉敷に向かった。倉敷川周辺にある大原美術館に着いたのは4時少し前で入館しても1時間ほどしか時間が無いため,倉敷川の周辺を散策した。倉敷は終戦時の爆撃に会わなかったそうで江戸時代の名残の街並みや大原美術館などの洋館が残っている。大正6年に倉敷町役場として建てられた倉敷館は改装中のため見れなくて残念だった。大阪冬の陣の時に備中国総代官小堀遠州は、徳川方の兵糧米を大阪に送る基地として川の周辺に陣屋を築いた。明治になりその跡地に倉敷紡績所が創設された。現在はアイビースクエアとしてホテルを中心とする複合観光施設となり,紡績工場時代の工場の外壁だった赤レンガはツタがからまって美しい外観だ。5時過ぎに岡山城に向かった。 |
 |
 |
 |
 |
| 旧倉敷銀行本店 | 倉敷館 | アイビースクエアとツタ | 岡山城天守閣 |
|
岡山城と後楽園は旭川に囲まれている,お城は河口から 7kmにあるためか引き潮の時には旭川は綺麗だが,満潮時は濁っていた。天守閣は第二次大戦時の空襲で焼失したため,再建されている。現存する月見櫓・西之丸西手櫓は国の重要文化財に指定されている。翌日,後楽園を朝7時30分の開園と同時に見学する。今回の旅行で唯一のシニア料金が適用され140円だ。江戸時代には後楽園にタンチョウヅルが飛来していたそうで,今ではゲージに6羽のタンチョウツルがいる。安土桃山時代にはソテツは異国情緒豊かな庭園樹として奄美黄島から持って来られ珍重されており,後楽園には当初から植樹されていた。明治時代に岡山県の県知事となった薩摩出身の知事が沢山のソテツを持ってきてその面積が広がった。江戸時代には後楽園の水は旭川を4km遡った地点で分流し水路で流し込み公園を巡回後,旭川に戻していたが,現在は地下水をくみ上げている。後楽園には茶畑,畑,田んぼがあり,鑑賞だけの庭園ではなかったようだ。江戸時代でも許可を得た農民なども庭園の見学は許されていたのは,領民に対するパフォーマンスかもしれない。小生の見学当日は,早乙女による茶摘みが模様されたが,時間の関係で見れなかった。9時過ぎには岡山城の天守閣周辺を見学し姫路に向かった。 |
 |
 |
 |
 |
| 後楽園灯篭 | 茶畑 | 後楽園の庭園 | ソテツ |
|
岡山から姫路に行くには,新幹線で20分くらいだが,新幹線以外に適当な交通の手段を見つけられなかった。前回姫路城を訪問したのは平成の大改修中(2011〜14年)だったので久しぶりだ。姫路城は明治時代に民間に払い下げられたが,落札者は瓦や釘などが大きくて民間で再利用できないとして権利を放棄した。このころ,陸軍省第四局長代理だった中村重遠(しげとう)大佐は,山県有朋陸軍大臣にこの素晴らしい姫路城を後世に残すために陸軍省の費用で修理・保存をすべきと意見書を提出し,姫路城の保存が決まった。また,第2次大戦では天守閣や西の丸に焼夷弾が投下されたが,不発弾であったり,すぐに消し止められたことにより今日の美しい姿が残った。明治と昭和の陸軍は考えが違う。天守閣は姫山(標高45m)の上に立っている。時間があったので天守閣周りの内堀を一周し裏側から天守閣を見ようとしたが,天守閣の裏側は急な崖で木々に覆われており建物は一切見えない。姫路城のお堀の水は船場川側から取り入れられ,内堀などいろいろな堀を流れているが,はっきりとした流路はわからないと城のガイドの人から聞いた。世界遺産のせいか外人の観光客も多いが,シニア割引なしだ。その後隣接する好古園を見学した。この庭園は元和4年(1618)造営の西御屋敷や武家屋敷、通路跡等の遺構の跡地を利用し平成に作られた日本庭園のため綺麗ではあるがなんとなくがっかりした。好古園の庭園には沢山の水が流れているが,地下水を循環させている。 |
 |
 |
 |
| 好古園 | 姫路城天守閣 | 大手門 |
|
次は明石に向かった。明石は瀬戸内海に面しており,魚の棚というアメ横みたいな魚の市場に行った。アメ横より少し安い気がしたが,ホタテの貝殻にホタテの身とその他の切身をのせてバーナで殻ごと焼いたのを500円で売っており,外人の観光客が並んでいた。高いと感じるが,外人には珍しいのかもしてない。ここでは明石焼きを食べた。明石では卵焼きといい柔らかいタコ焼きという感じでアツアツを出汁に着けて食べる。卵,沈粉(蛋白質を除いた小麦粉),タコをタコ焼き風に焼き,10個で600円だった。卵焼きを売る店は結構多い。お腹が溜まった所で明石天文台に向かう。天文台は丘の上にある。ここから瀬戸大橋が良く見える。明石は長崎に似て海からすぐ坂道になっている,ただし長崎程高い山ではなく台地状になっている。また,教会とお寺が多いのも似ている。江戸時代初期には明石は譜代大名である小笠原10万石が目の前の淡路島と明石の間を航海する徳川を快く思わない西国の大名の軍船がいないか監視していた。天守台はあるものの天守閣は作られなかったようで,巽櫓(たつみやぐら)、坤櫓(ひつじさるやぐら)が現存し国の重要文化財に指定されている。小笠原家は礼法で有名な小笠原流の家元だ。築城の後見役であった姫路の本多家の客人の宮本武蔵は樹木屋敷(城主の遊興所)や本松寺の庭園の造営や町割りに関わったそうだ。ただ現在樹木屋敷は陸上競技場となり存在しない。 |
 |
 |
 |
| 卵焼き | 明石城の櫓 | 本松寺の庭園 |
|
|
明石と言えば日本標準時東経135度だ。標準時子午線は天文観測によって決められ,地図や
GPS
で用いられる測地経緯度(地理学的経緯度)による経線とは異なる。明石市付近では、約
120m ずれている。明石には日本標準時東経135度の標識が7か所あり,山陽電車人丸前駅のホームにひかれた
135 度の白線と明石市立天文科学館を見て須磨のホテルに向かった。
|
| 天文科学館と白線 |
|
翌朝はホテルの近くの須磨寺を参拝した。この寺は源義経が一の谷の戦い時に本陣としたお寺だ。お寺には平敦盛と熊谷直実の像や,敦盛が持っていた青葉の笛,高麗の笛,敦盛の首塚などがあり,源平のゆかりのあるお寺だ。朝にも関わらず,お参りの人や対応するお坊さんの数も多く,出店のお店いくつか見られ,お寺と住民が一体になっている気がした。
|
 |
 |
 |
| 平敦盛と熊谷直実の像 | 高麗笛と青葉笛 | 須磨寺の仁王門 |
その後,クラス会のメンバーと貸切バスで大阪難波に向かった。道頓堀は人が多い。難波花月の前でしばらく呼び込みを見て,黒門市場に向かう。この市場はひところさびれていたそうだが,店主たちが中国語や韓国語の勉強をしたそうで今はこれらの国の観光客が多い。メロンの中身をくりぬいて中にいろいろな果物を詰め込んだのを食べている観光客が多い。日本の名物と思っているのかもしれないが1000円は高すぎると思う。苔でびっしり覆われた水掛地蔵や法善寺横丁を見て通天閣に向かう。通天閣に登るのは初めてだ。何度かエレベータを乗り換えなければいけないが,乗り換えるためにはお土産屋の中を歩き回らねばならずさすが大阪と感じた。展望台から下を見ると茶臼山が見える。冬の陣で徳川家康が陣を張った山だ。先には大阪城が肉眼でも見える。通天閣近くのジャンジャン横丁で串カツを食べる。15m程の行列で待っているお店もあるが,予約してあったお客の少ない店へ向かう。大阪名物の串カツだが普通の串カツで一度漬けが名物かと思う。その後新大阪駅に向かいクラス会は散会した。
 |
 |
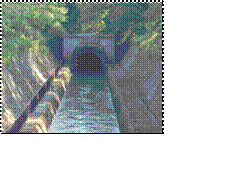 |
| 道頓堀と戎橋 | 通天閣 | 琵琶湖疏水 |
|
予定より早く3時過ぎに大津に向かう。大津に着きそのまま園城寺三井寺に向かうも5時少し前に着いたので見学を止め,三井寺の地下を流れる琵琶湖疏水を見学した。この水路は京都に水を送るために作られ,第1疏水は明治23年(1890),第2は明治45年(1912)に完成し,毎秒23.7m3の水量を流している。(利根大堰の総取水量は毎秒88.6m3))JR大津駅から琵琶湖へ行くには下り坂で見えている。琵琶湖は回りを山で囲まれており約460本の川が流れ込んでいるが,流れ出るのは瀬田川のみである。1万年前は現在より水位は約5m低かったと言われている。過去大規模な地震が少なくとも4度あり,その度に瀬田川の流入口付近の川床が上がりさらに付近の山が荒廃し土砂が流れ込むため瀬田川への流出が少なくなり,安土桃山時代から明治の初めまでの水位は現在より120cm程高かったようだ。明治29年(1896)に彦根や大津では大洪水があった。このため土木技師沖野忠雄が中心となり瀬田川の浚渫や川幅の拡張,瀬田川の水量を調整する堰の設置,瀬田川に続く淀川の堤防を整備する治水対策を行い,現在のように琵琶湖の水位を低く調整した。翌日は安土に向かう。安土には普通電車しか止まらない。駅から2時間500円のレンタル自転で安土城に向かう。現在安土城のある安土山(標高199m)の麓は,干拓され畑だが,築城当時はお城の東側,北側,北西部は湖に突き出ていたらしい。安土城の天守台は安土山の山頂にあるが,山の麓からは112mの高さである。天守閣は本能寺の変のすぐ後に炎上したそうだが原因は判っていない。大手門から幅6m程の直線の石段が180m程続き目立つ。大手門から少し上ると左に秀吉,右に前田利家の屋敷跡がある。石段の幅は上に登るほど狭くはなるが,階段が延々と続き大手門から天守台まで20分かかる。石段の石にいくつかの石仏があった。見る事は無かったが,案内板には墓石も使われたとあり,石は強権で集めたようだ。 |
|
信長は延暦寺を焼き討ちしたので,仏教は信じていないと思っていたが,なんと,築城当時から安土城内に�見寺(そうけんじ)という臨済宗のお寺があった。現在は,三重の塔と仁王門が残っているだけだが,修理中で近寄れなかった,また,天守閣の中に吹抜けがあり,そこに宝塔があったのではないかという説もある。さらに驚く事には安土城の現在の所有者は�見寺だ。現在のお寺は立ち入り禁止で見る事は出来なかった。お城の掃除をする人に聞いた話では,信長を弔っているそうだ。また,山頂近くの二の丸跡には秀吉が作り江戸時代に再建された信長の廟があるが,年に何度か美しい白蛇を見る事があり,濃姫が蛇になり信長の霊を守っていると噂しているということも聞いた。民間の所有という事で特に天主台や本丸付近は痛んでおり,保存と発掘があまり行われていないようだ。 |
 |
 |
 |
| 安土城の大手道石段 | 安土城の天主台 | 安土城天主閣の模型 |
|
安土駅の近くにヴォーリズが大正時代に設計した西洋建築の家がある事を見つけ向かう。ヴォーリズは、アメリカに生まれ、日本で数多くの西洋建築を手懸けた建築家であり,ヴォーリズ合名会社(のちの近江兄弟社)の創立者の一人としてメンソレータム(現メンターム)を広く日本に普及させた実業家でもある。住友家第二代総理事伊庭貞剛(いばていごう)の㈣男慎吉(しんきち)が住んだこの住居の外観は主に洋風で内部は1階が和風,2,3階が洋風だったようだが,その後より和風に改築されたようで外観も昔の写真と異なる。現在は市の所有でボランテイア団体が管理している。ヴォーリズとその仲間は日本に沢山の建築物を残している。 |
 |
 |
 |
| 改装前の外観 | 現在の外観 | 居間 |
|
最後の訪問地である彦根に向かう。関ヶ原の戦いの後,井伊直政は石田三成が築いた佐和山城に入ったが,その子の代に目の前の彦根山(標高50m)に彦根城を築城した。 彦根城の天守は国宝指定された5城のうちの一つである(他は犬山城、松本城、姫路城、松江城)。彦根城の天守閣は解体寸前に明治天皇の指示により解体を免れた。進言したのは大隈重信という説と天皇の従妹のかね子(住持攝専夫人)という説がある。標高が低いせいもあり山頂にある天守閣一帯まで楽に登れる。ただ,最後の天守閣一帯に行く道は一本の橋しかなく,その橋を壊す事で籠城出来るようにしてある。天守閣一帯の外側に向いた城壁の壁は厚く鉄砲に備え石を埋め込んであるそうだ。 |
 |
 |
 |
| 天守閣にかかる橋 | 彦根城の天守閣 | 玄宮園 |
|
玄宮園は後楽園と同様庭園であるが田んぼがあった。井伊家の藩主は参勤交代で江戸から彦根に帰る時には中山道を籠で戻るが,お城の近くに来ると馬に乗り換えて城内に戻ったそうだ。田や馬は藩に対するパフォーマンスだったかもしれない。タイミングよくお城でひこにゃんを見る事が出来た。江戸時代には彦根城の堀の水は琵琶湖の水を引いていたそうだが,現在は先述したように琵琶湖の水位を低くしてあるので,お堀の水はポンプでくみ上げているそうだ。お城の近くには昔ながらの街並みを残しており朝鮮通信使が泊まった宗安寺などある。朝鮮通信使が来ると慶長時代に日本に連れて来られた朝鮮の人やその子孫が朝鮮の事を聞くためにお寺に尋ねて来たそうだ。悲しい話だ。彦根を最後に米原経由で家に向かった。 |
 |
 |
 |
| 井伊直政の像と彦根駅 | 宗安寺 | 挨拶するひこにゃん |
All right reserved by Ikigai-Inaga-NetClub
伊奈いきがいネットクラブ
